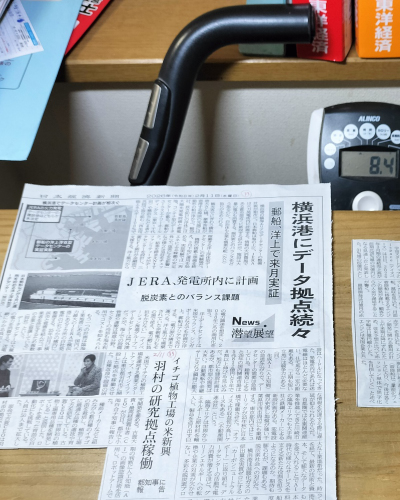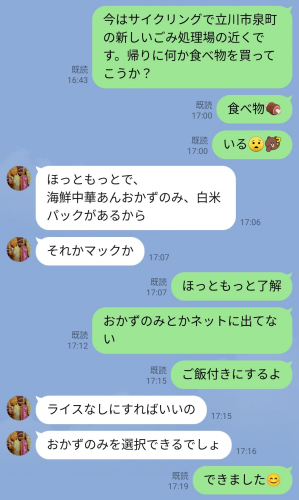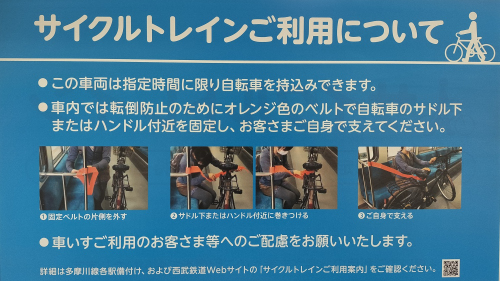2/23 11:00出発!

11:20 JR五日市線 多摩川橋梁

12:24 是政橋

12:37 西武多摩川線 サイクルトレイン

12:51 武蔵境駅

12:57 Porco rosso号 と オイラ

13:03 多摩湖自転車歩行者道

13:46 多摩湖(村山貯水池)

15:02 野山北公園自転車道
(羽村・山口軽便鉄道跡)

15:28 お弁当屋さん
本日の散走距離:54km
探査機:Porco rosso号
( DAHON K3 )
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2/22 娘が帰省していて今朝帰りました。
嫁様が駅まで送って、帰宅すると、
「マックあるよ」とソーセージマフィンが。

ありがたや。 _(_^_)_
玄関先で美味しくいただきました。
10:45頃に出発。暖かいけど風はある。
羽村の堰より多摩サイ左岸。
最寄りの自販機でアクエリアス購入。
ボトルケージに納まりがいい容器ですね。
散歩、ウォーキング、ランナー、野球少年、サイクリスト。
場所によっちゃ多摩サイはカオス。
道幅狭いからね、バックミラー装着は正解。
抜くのも抜かれるのも譲り合わないと。
お婆ちゃんの団体が道を譲ってくれた。
熊除けの鈴が役に立っております(笑)。
「ありがとう」 「どういたしまして」
小径車は歩行者に近い自転車かもね。
暑くなってきました。

11:34 立日橋でウィンドブレーカーを脱ぐ。
アクエリアスをゴクゴク飲んじゃう。美味い!
本日はマイペースに徹してオーバーペースを避け、
譲る、追わない、逃げない、僕は僕、君は君。
と戒めて呑気にクルージング。
国立でGiosのミニベロ爺様!の追撃があり、
来るかと思ったけど来なかったな。
(それも楽しみなんだけどね)
府中の郷土の森付近の道端に、
バックが置いてあるのかと思ったら、
お婆さんがうつ伏せで倒れていた。
Σ( ̄□ ̄|||)
お仲間のお婆さんが助け起こしている。
止まって声を掛けたら大丈夫とのこと。
通りすがりの親父さんも加わって来た。
故に僕はその場を後にします。
怪我してないといいけど、ヤヴァイな。
で、ちょっとトイレがヤヴァイっす。
何故か脳裏にはSHOW-YAの
限界 LOVERSが響いてきた。
「限界までぇ~♪限界までぇ~♪」
FORMULA SHELL の CMですわ。
(アラン・プロスト アイルトン・セナ 時代)
古いなぁ~ ( ´艸`)
オイラのガソリンノズルじゃないけど。
ハイオク満タンだぜ!スパーク⚡⚡⚡
多摩水道橋で右岸へ渡り、

12:43 二ヶ領宿河原堰でトイレ休憩。
多摩サイはトイレが割とあって助かる~。
で、水分&カロリーメイトで補給っすよ!
多摩川大橋で左岸へ渡ります。
時々、向かい風で脚に来ちゃいます。
時々、追い風で風に乗っちゃいます。
不安定な強風もいつもの多摩サイです。
よし、羽田に到着っす。

14:15 ANA 駐機スペースがよく見える。
多摩川スカイブリッジを渡って、


14:20 いつもの都県境プレートにて。

14:32 KEIKYU 小島新田駅 着。
電車に乗って帰りま~す。
無理せずマイペースで走ったので余力あり!
まぁ、でもいい運動ですね。
これぞ有酸素運動ってやつでしょうか。
もうすぐ還暦のおっさんは、
運動しないと病気になっちゃうので、
僕にとって自転車はホント大事です。
健康が維持できる自転車 LOVE !
本日の走行距離:61km
探査機:Grazing号
( ESR PURSUER Disk )